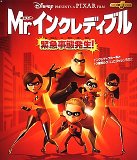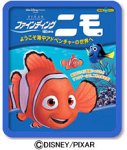私自身は、これまでのプレゼンテーションはなんとか原稿を読まないでおこなってきたのですが、壇上に立つと緊張のあまりに頭が真っ白になって、まったく言葉が出てこないという事があります。幸いなことに、私は完全にその状態になったことはないのですが、なりそうになりかけたことはあります。
そのため、私の若い衆には、1枚目のスライドは図だけ載せて、説明を考えてしゃべるというパターンのスライドは避けるべきだとアドバイスしています。スマートではありませんが、1枚目のスライドは、そのままスライドを読むだけのようなスライドにすることを勧めています(つまり、箇条書きの文章)。これだと、1枚目はそのまま読むだけでいいという安心感が出ますし、1枚目のスライドを乗り切れば、自分のしゃべりのペースが出てきて、プレゼンテーションを乗り切れることが多いように思います。
もちろん、原稿は事前に作成して、十分な練習を繰り返すことが重要です。たとえ、日本語のプレゼンテーションであろうと、事前の練習なしでうまくいくことはないと私は考えています。
さて、問題は英語のプレゼンテーションです。英語のプレゼンテーションの場合、たとえ1枚目のスライドを乗り越えられても、その後、どのスライドでも頭が真っ白になる可能性があります。英語のプレゼンテーションを原稿を読むことなしにするための裏技を紹介しましょう。
頭が白くなってしまったときのために、手元に原稿を持っておくというのは確かに一つの方法なのですが、いったん原稿から目を離してしゃべり始めてしまうと、途中でちらっと原稿を見るとことは実際にはほとんど不可能です。原稿をあれこれめくっているうちに、聴衆には原稿を読んでいることがバレバレになります。
おすすめのテクニックは、しゃべるべき単語やフレーズをなるべく、スライド中に書いてしまうと言うことです。たとえば、mRNA expression for
XX in kidneyでそのスライドの説明を始めるなら、それをそのままタイトルにしてしまうとか、しゃべるべき実験結果を文章のままスライドに書いてしまうというのも一つの方法です。あんまりやりすぎるとスライドがくどくなりますが、背に腹は代えられません。
そして、とっておきの方法は、Microsoft 2004 for Macに入っているPowerPoint 2004から採用された発表者ツールを利用する方法です。このモードを選択するとスライドスクリーンにはスライドのみが映写されますが、手元のモニターにはノートが表示されます。つまり、紙の原稿を持ち込まないでも、手元のモニターには原稿が表示されているので、頭が白く飛んでしまったときには手元のモニターに表示された原稿を読んで急場をしのげます。それでも、すべて原稿を読んだのでは、「原稿を読まない」プレゼンテーションの利点はスポイルされますので、あくまでも、緊急事態と考えて頂ければよいと思います。ただし、学会によっては、自分のコンピューターをPodium(演台)に持っていくことは許可しない学会もあります。今回の学会でも2人の方がこの発表者ツールを使っていました。
いろいろ姑息なテクニックを紹介しましたが、正当的に英語でのプレゼンテーションのトレーニングを積むこともお忘れなく。→自分。